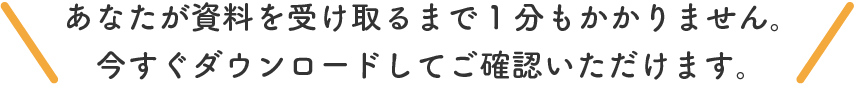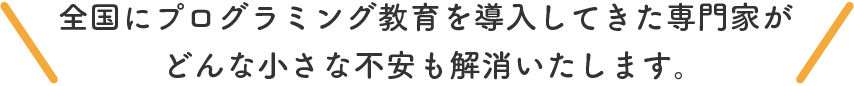プログラミング教育が引き出す、子どもの新たな一面

千葉しらゆり幼稚園の特色
千葉県千葉市に位置する千葉しらゆり幼稚園は、「子どもの生きる力を育てる」ことを大切にし、子ども一人ひとりが持つ力を最大限に伸ばすための日々の保育に取り組まれています。専門講師による英語や音楽、体育といった多彩な活動を通して、子どもたちの「楽しい」「やってみたい」という純粋な好奇心を育むことを重視されています。 また、学びの場もたくさん提供されていますが、単に知識を詰め込むのではなく、様々な経験を通して「生きた知識と知恵」を身につけることを大切にされています。例えば、年中・年長組を対象とした「オープン保育」では、学年の垣根を越えて、木工や音楽といった子どもたちが自ら選んだ活動に夢中になれる時間を設けています。
目次
導入経緯|小学校での学びに繋がる、初めてのプログラミング体験
Q. ご導入のきっかけは何だったのでしょうか?
近年、小学校からプログラミング教育が必修化されました。これにより、子どもが早い段階でテクノロジーに触れるのは、当たり前の時代になっています。保護者の方々からも、そうした変化に対する期待や関心の声を聞く機会が増えています。
そこで私たちは、本格的な学習が始まる前に「準備」をさせてあげたいと考えました。何より大切なのは、まず「プログラミングって楽しい!」と子どもに感じてもらうことです。なぜなら、この最初の楽しい経験こそが、将来の主体的な学びに繋がるからです。その思いが、導入の大きなきっかけとなりました。
導入の決め手|多彩な専門教育と両立できる、柔軟なカリキュラム
Q. 導入の決め手は何だったのでしょうか?
当園の特色は、英語や音楽、体育など、それぞれの専門講師をお招きして行う多彩な保育活動です。このように、園児一人ひとりの経験を豊かにするための時間をすでに多く設けています。そのため、新しい活動を導入するにあたっては、既存のカリキュラムを圧迫しない柔軟性が何よりも重要でした。
その点、このカリキュラムは外部講師を新たに依頼する必要がありません。そして、園の教育方針を熟知している私自身が、日々の様子を見ながら時間を調整して進められます。この点が、当園のスタイルにまさに合っていました。加えて、母体がIT会社であるという専門性への信頼感も、導入を後押しする大きな決め手になりました。
導入後の変化|子どもが自ら学び、成長する授業へ
Q. 実際に授業を始めてみて、子どもの様子はいかがですか?
素晴らしい変化の連続で、私たち自身も驚いています。例えば、「今日はプログラミングがある!」と、朝からワクワクして登園してくる子も多く、その自主的な姿はとても嬉しいものですね。
特に印象的だったのは、ある園児の変化です。その子は、普段は紙に絵を描くのが少し苦手でした。しかし、デジタルなら何度でも気軽にやり直せます。その安心感からか、今では夢中になって自分の世界を表現しています。
さらに、授業の最後には発表の時間を設けています。以前は人前で話すのが得意ではなかったその子も、今では自信を持って作品をいきいきと見せてくれるのです。このように、積極的に発表する姿を通して、私たちも知らなかった子どもの新たな一面を発見できるのが、何よりの喜びです。

今後の展望|プログラミングで培う、未来を生き抜く力
Q. 今後プログラミング教育を通して、どんな子に育ってほしいですか?
このプログラミングでの「まずはやってみる」という経験を通して、大きな自信をつけてほしいと願っています。ここで育んだ「自分で考えて形にする力」。そして、「挑戦する楽しさ」。これらは、小学校に上がって新しい学習に臨む際の、きっと大きな支えになるはずです。今後も、ロボットなどを活用しながら、子どもが未来に向かってワクワクできるような体験を増やしていきたいです。

取材を終えて
取材を通して、千葉しらゆり幼稚園様の温かくも力強い教育理念が、プログラミングというツールで見事に実践されていると感じました。
それは、単にITスキルを学ぶのではありません。試行錯誤の中で「乗り越える力」や「表現する喜び」、さらには「仲間を認め合う心」を育む、まさに「生きる力」の教育でした。
また、プログラミング教育を支えるICT環境も印象的です。中でも、電子黒板は特に効果的に活用されていました。園児の作品を定期的に紹介することで、次への創作意欲を高めているそうです。実際に、使用されている電子黒板は複数画面を同時に接続できる高性能なものでした。そのため、発表の際のタイムロスも少なく、子どもが次々と手を挙げて発表したがる活気ある授業に繋がっているのだと感じました。
園にあふれる子どもの「楽しい!」という声。そして、その成長を心から喜ぶ先生方の笑顔。これらが、これからの幼児教育の可能性を明るく照らしているように感じられました。ありがとうございました。